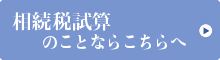相続対策としての生前贈与(現金等)による相続税圧縮効果の試算
2023.12.08更新
★前提条件を次の相続内容で試算
*所有財産:3億円
*受贈者 :配偶者と子供2人と孫4人
*遺産分割は法定相続分とし、配偶者控除を適用
[ケース1] 何も相続対策をしない場合
*課税財産額 300,000,000円
*基礎控除額 ▲48,000,000円
*課税対象額 252,000,000円
*算出相続税額 配偶者33,400,000円、子11,900,000円×2
=23,800,000円
*配偶者の税額軽減 ▲33,400,000円
*納付税額 23,800,000円 → ①
「ケース2」 相続対策として配偶者、子2人、孫4人に毎年110万円ずつ10年間贈与した場合
*課税財産額 223,000,000円 (10年間の贈与財産額77,000,000円をマイナス)
*基礎控除額 ▲48,000,000円
*課税対象額 175,000,000円
*算出相続税額 配偶者19,250,000円、子6,750,000円×2
=13,500,000円
*配偶者の税額軽減 ▲19,250,000円
*納付税額 13,500,000円 → ②
①-② 税圧縮効果 10,300,000円
課税財産額が大きいほど税圧縮効果も大きくなります。
注)贈与財産の相続財産への加算は考慮していません。