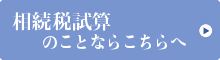包括遺贈と特定遺贈
2022.01.31更新
遺言によって相続人以外に財産を譲り渡すことを「遺贈」といいます。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類がありますが、どのように違うのかを説明します。
まず、包括遺贈とは、遺産の全部又はその分散的割合(例:全遺産の3分の1)、ないし、抽象的割合を指示するにとどまり、目的物を特定しないでする遺贈です。
なお、包括遺贈には遺贈する財産が変化しても一定の割合を特定の相手に遺せるというメリットがありますが、反面、遺贈者に借金(債務)があれば、遺言の割合に応じてその債務を負うというデメリットがあります。
また、相続人がいない人の場合は、養子縁組をする以外は、遺言で自分の財産全部を包括的に遺贈する人を決めて思いを遺すことができます。(全部包括遺贈)
これに対し、特定遺贈は、目的物を具体的に特定してする遺贈です。(民法964条)
例えば、自宅の土地を誰々に遺贈する、というように遺産のうち特定の財産を指定して受遺者に譲り渡すことをいいます。
このように譲り渡す財産が特定されているため、包括遺贈に比べると法定相続人との間で協議する必要がないので、トラブルが生じる可能性は高くありません。