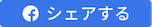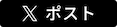相続税申告
2022.01.06
民法改正(成年年齢引下げ)と相続税・贈与税

現行の民法第4条では、「年齢20歳をもって、成人とする」と定められています。
しかし、民法の一部改正の法律が施行される令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
この改正により相続税・贈与税においても、20歳を基準としているものは18歳が基準となり、以下の通り改正されることとなります。
1相続税の未成年者控除
相続人の中に未成年者がいる場合、相続税が一定額控除されますが、その控除額が次の通り改正されます。
*改正前:法定相続人が20歳未満の者である場合には、20歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除
*改正後:18歳に達するまでの年数(1年未満の端数は切り上げ)に10万円を乗じた金額を相続税額から控除
また、2回目の未成年者控除においても控除可能額に影響があります。
2贈与税の相続時精算課税制度
相続時精算課税制度の適用を受けることができる人は、贈与の年の1月1日において、18歳以上の人となり、従来の20歳から2年早く適用が受けられることになります。
3贈与税の特例贈与(特例税率)
直系尊属(父母や祖父母)から贈与を受けた場合の贈与税の特例を受けることができる人は、贈与の年の1月1日の年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられます。
また、一般的に遺産分割協議においては、現行では20歳以上の相続人でなければ遺産分割協議に参加できませんが、令和4年4月1日以降はその時点で18歳以上の相続人であれば同協議に参加することができることになります。
RELATED ARTICLE関連のおすすめ記事
葬儀費用の相続財産からの控除
一般的に葬儀費用とは、故人を弔う一連の儀式や埋葬のためにかかった費用をいいます。そして、相続税では葬儀にかかった費用は…
2022.11.10
相続人全員の話し合いがまとまらず、未分割のままで申告することとなりました。相続財産が多いので、納税額が相当な金額になりそうです。ただし、相続財産の金融機関の預金口座が凍結されているため、納税資金がない状態です。
金融機関(銀行等)は、相続開始の情報を得た場合に、故人名義の口座(預貯金等)を凍結して、入出金ができないようにしてしま…
2022.08.29
「小規模宅地等の特例」の賢い活用法
「小規模宅地等の特例」は店舗・事務所やアパート、駐車場などの賃貸している土地を相続する場合に適用されます。賃貸している…
2023.09.25