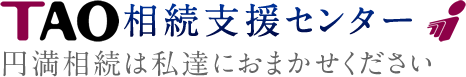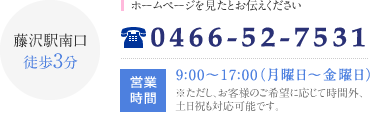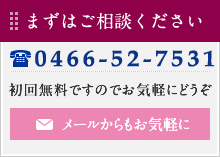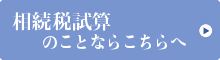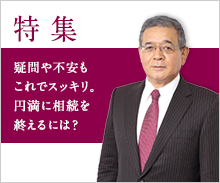Q:相続した土地の一部が都市計画道路にかかっています。どのように評価したらよいでしょうか
2024.07.22更新
Q:相続した土地の一部が都市計画道路にかかっています。どのように評価したらよいでしょうか
A:都市計画法に基づき整備することが決定した道路のことを「都市計画道路予定地」といいます。この場合、都市計画法では道路の名称や建設する位置・区域、種別や車線の数などを定めることとされています。
「都市計画道路予定地」に、個人の私有地を含むエリアが存在すると都市計画法によって建築制限がかけられ、その後は、都道府県等の許可を受けなければ、自由に建物を建てることはできなくなります。
なお、この場合の建築制限とは主に次のとおりです。(都市計画法53条~57条)
① 階数が2以下で地階を有しないこと
② 主要構造部(壁・柱・梁・床・屋根・階段)が木造や鉄骨造、コンクリート造などであること
③ 建物は容易に移転、除去できるものであること
ご質問のように相続した土地が「都市計画道路予定地」として建築制限がかかっている宅地の場合、宅地としての利用価値が下がります。このような土地の場合、財産評価通達24-7において、通常の宅地の評価額に「地区区分」、「容積率」、「地積割合」の別に応じて定める補正率を乗じて減額することができる規定が適用されると思われます。
なお、具体的な補正率は、上記の区分別に最高0.50~最低0.99まで24段階ありますので、財産評価通達24-7に規定する補正率表をご確認ください。
このように都市計画道路予定地内の土地は、評価対象地の地域性や画地条件の他、法的な建築制限などにより、減額率が大きく変わるものです。したがって、まずは、役所に出向いて地積割合などを確認し、場合によっては正確な測量を行う必要があることを覚えておきましょう。