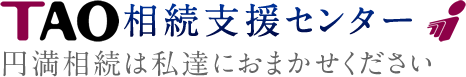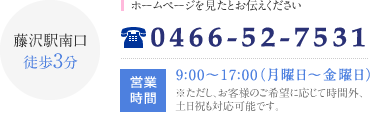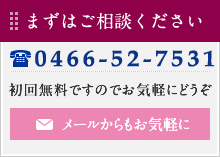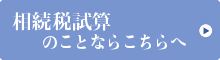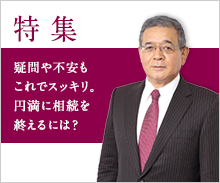Q:贈与税の配偶者控除の特例について詳しく教えてください。
A:「贈与税の配偶者控除」は「おしどり贈与」とも呼ばれ、「居住用不動産を贈与又は取得資金を贈与」したときに、夫婦間に認められている贈与税の優遇制度で、2,000万円までなら贈与税を免除するという制度です。贈与税には年間110万円の基礎控除がありますから、合計で2,110万円までが非課税となります。
特例を受けるための要件は、次の3点です。
(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
(2)配偶者から贈与された財産は、 居住用不動産であるか居住用不動産を取得するための金銭であること。
(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。
(注1「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地もしくは土地の上に存する権利または家屋で国内にあるものをいいます。
(注2)配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。 (国税庁)
例えば、夫名義のマイホームの一部を妻に贈与(おしどり贈与)した後に、夫が亡くなった場合、その贈与部分は相続財産にはなりませんので、相続税が軽減されるメリットがあります。
一般的に相続開始前3年以内に行われた贈与については、相続財産として相続税の対象になりますが、おしどり贈与の場合には相続財産になりません。また、マイホームを売却して利益が出たときに、3,000万円控除される制度がありますが、夫婦がそれぞれ活用できると6,000万円が利益から差し引かれます。
なお、注意が必要なことは、不動産取得税や登録免許税がかかりますし、毎年、固定資産税や都市計画税の請求がくることになります。
贈与税の配偶者控除の特例(相法21条の6)チェックシート
(参考:国税庁)
1 贈与者(財産をあげた方)は、あなたの配偶者ですか。
2 婚姻の届出をした日から贈与を受けた日までの期間は20年以上ですか。
3 過去に、この特例を受けたことがありますか。
4 贈与を受けた財産は不動産(土地等・建物)又は金銭ですか。
5【不動産の贈与を受けた場合】その不動産は国内にある不動産ですか。
【金銭の贈与を受けた場合】その金銭を翌年3月15日までに国内にある居住用不動産の取得に充てますか
6 その不動産は専ら居住の用に供しますか。
7 その不動産に現在居住しているか、または翌年3月15日までに居住する予定ですか。
8 今後、ひき続きその不動産に居住する予定ですか。